被爆80年の原水爆禁止世界大会長崎に参加して
私は宮前原水協と新婦人宮前支部の代表として長崎大会の3日間に参加させていただきました。
8月7日に行われた「被爆80年長崎のつどい」のテーマは「被爆体験の継承と未来」でした。第一部は3つの部分からなり、最初の「長崎原爆の実相普及」では、長崎総合科学大学名誉教授の大矢正人さんが、長崎原爆の被害の概要を説明し、被爆直後の貴重な撮影写真や記録動画で、原爆のきのこ雲や、焼け野原となった長崎の町や悲惨な人々の姿を伝えました。今までに見たことのない光景に思わず息をのみました。
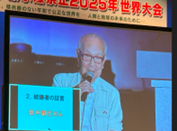 続く「被爆者の証言」では、日本被団協の田中熙巳(てるみ)さんが登場され、インタビュー形式で、13歳での被爆した際の体験を語られました。被爆直後の行動、救護所での様子、被爆3日目に母と爆心地にはいって伯母らを荼毘に付したこと、家に帰る道で悲惨な状況などを目の当たりに見て、父と同じ軍人志望だったが、こんな戦争をやっていいのかと思ったことなどを語りました。9月に再開した学校で家族を失った同級生が、「私一人です。みんな死んでしまいました」と報告したことを涙で声をつまらせて話された時は、田中さんの思いに心を打たれました。苦労しながら大学に行き、学生運動や組合運動に加わりながら、被爆者者たちの仲間を助けようと被団協の活動を始め、核兵器廃絶と被爆者の援護の運動をずっと続けてきたこと、「ノーベル平和賞受賞は、嬉しいがこの運動に精一頑張った人たちがもういない、あと10年早く授賞してくれたらと」との言葉も印象に残りました。「受賞を国内的にも国際的にも活用して、被爆者たちが叫び続けてきた運動に結集してほしい」と訴えると聴衆は大きな拍手で応えました。
続く「被爆者の証言」では、日本被団協の田中熙巳(てるみ)さんが登場され、インタビュー形式で、13歳での被爆した際の体験を語られました。被爆直後の行動、救護所での様子、被爆3日目に母と爆心地にはいって伯母らを荼毘に付したこと、家に帰る道で悲惨な状況などを目の当たりに見て、父と同じ軍人志望だったが、こんな戦争をやっていいのかと思ったことなどを語りました。9月に再開した学校で家族を失った同級生が、「私一人です。みんな死んでしまいました」と報告したことを涙で声をつまらせて話された時は、田中さんの思いに心を打たれました。苦労しながら大学に行き、学生運動や組合運動に加わりながら、被爆者者たちの仲間を助けようと被団協の活動を始め、核兵器廃絶と被爆者の援護の運動をずっと続けてきたこと、「ノーベル平和賞受賞は、嬉しいがこの運動に精一頑張った人たちがもういない、あと10年早く授賞してくれたらと」との言葉も印象に残りました。「受賞を国内的にも国際的にも活用して、被爆者たちが叫び続けてきた運動に結集してほしい」と訴えると聴衆は大きな拍手で応えました。
「被爆者運動の歴史と被爆者のたたかい」では、冒頭に、被爆後占領軍と日本政府により原爆被害の隠蔽と被爆者の放置がなされたことを、大塚一敏さんが告発。続けて、1954年のビキニ事件を契機に原水爆禁止運動が高まり、被爆者も声をあげ始め、広島で開催された第1回原水爆禁止世界大会では、長崎から山口美佐子さんが、翌年の長崎で開催された第2回世界大会では、渡辺千恵子さんが、被爆し傷を負った体で核兵器の恐ろしさを訴えたことが、当時の映像を交えて紹介されました。1970年代以降の被爆者の国連の場での活動について、被団協代表理事の横山照子さんが説明し、1882年第2回国連軍縮特別総会での山口仙二さん、2010年5月NPT再検討会議での谷口稜曄(すみてる)さんらの演説が、映像や朗読で再現されました。 また、牧山敬子さんの勝訴まで13年にわたる長崎原爆松谷訴訟についての報告や、日本被団協田中重光さんによる、平和賞受賞後の1月のスペイン・フランス遊説について写真を交えての報告がありました。これらの報告から、本当に多くの人が連帯して長い闘いをたたかって来られたことをあたらめて知り、活動に頭がさがるとともに、被爆体験とこうした道のりを伝えていくことが大事だと思いました。
第二部では、車椅子で活動された長崎の被爆者渡辺千恵子さんの壮絶な半生を歌う合唱組曲「平和の旅へ」が、高校生も交えた合唱と朗読で演奏され、会場は感動に包まれました。この長崎の集いの現地参加は2100人、オンライン参加は500人でした。
2日目は、被爆の実相普及や、被爆者援護がテーマの第3分科会に参加しました。98歳の築城(ついき)昭平さんからは、「18歳で被爆して寮や近所の方がなくなり奇跡的に生き残ったが、核兵器が戦争で使われたら人類は滅亡する、どんなことがあっても反対しなかればならない、それが言いたいため死ねない。」と生の声を聞かせていただきました。
被爆者の方々に寄り添うソーシャルワーカーをされ今は被団協の相談員の原玲子さんは、差別や貧困に苦しむ被爆者の事例や、被爆者援護のための活動の歴史を説明されました。「運動によって少しずつ援護の対象を広げてきたが、原爆の放射能被害に限定され、遺族や亡くなった方への補償はされていない、国家補償(国が起こした戦争による被害は国が責任をもって補償すること)がなされなければならない。」と述べられました。「被爆者の方の被爆状況も、生きた歴史も一人一人事情が異なる、一人でも多く被爆者の話を聞きたい、それが被爆者にとっても援護となる」という言葉は、長く被爆者を支えてこられた原さんの思いをよく表わしていました。被爆体験を聞き取り伝えることの意味があらためてわかった気がしました。他にも田中重光さん、今年100歳になる女性の被爆者の被爆体験の報告があり、核兵器は絶対あってはならない兵器だとの思いを共有しました。
午後の後半は、もうひとつの「被爆遺構めぐり」の分科会に参加し、平和公園付近の原爆の遺構、被害にあった山里小学校や、旧浦上天主堂の北側の鐘楼部分、永井潔医師が晩年を過ごした如己堂(にょこどう)などを案内していただきました。

3日目の「ながさきデー集会」は、現地参加 3200人、オンライン参加700人と報告がありました。登壇者、特に海外からの多くのゲストの方に大きな励ましと力強いメッセージをいただきました。最後は、激動の時代における「希望の光」となっている核兵器禁止条約を力 に、「核兵器のない平和で公正な世界」への道を切り拓いていきましょう、今こそヒロシマ・ナガサキの「被爆の実相」をひろめ、核兵器の非人道性を告発していきましょう、などと訴える「長崎からのよびかけ」を採択しました。会場には若い人も目立ち、被爆80周年にふさわしい力強いメッセージにあふれた希望の見える大会だったと思いました。これからもできることを精一杯やっていこうと決意しました。
なのはな班 住広昭子